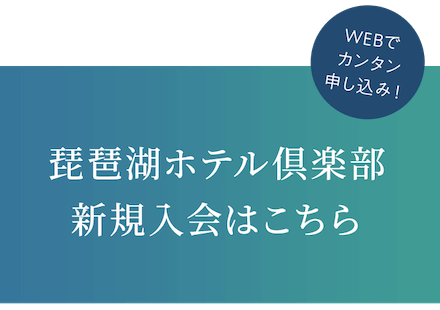Banquet / MICE 宴会場・会議
設備・宴会オプション Banquet Option
ご宴会やパーティをより楽しく、
華やかに盛り上げる演出を
オプションにてご用意いたしております。
また、各種映像・通信設備やサービスなど、
お客様のさまざまなご要望に柔軟にお応し、
快適なご宴会をサポートいたします。

各会場ごとの専用回線による通信サービスで
オンライン会議やイベントがスムーズに
これまでの共有型比べ、高速かつ安定したインターネット環境で、オンラインイベントやMICEなど快適な「リゾート×ビジネス」というスタイルの実現をサポートします。
※宴会場での光回線のご利用には、別途回線使用料および有線LANケーブル代がかかります。一部サービス対象外の宴会場がございます。詳しくはお問い合わせください。
主な設備
| 音響設備 |
|
|---|---|
| 照明設備 |
|
| オペレーター |
|
| 会場装飾 |
|
| 司会・音楽 |
|
宴会オプション
-

江州音頭
江州音頭は古くから滋賀県に伝承される民謡で、滋賀県内だけでなく近畿各地でも盆踊りなどで歌い継がれています。七五調の歌詞と軽快なメロディが江州音頭の特徴です。
-

琵琶湖周航の歌
琵琶湖の美しい自然と周航のロマンを情緒豊かに歌い上げたこの歌は大正6年に高島市今津で生まれ、今もなお、多くのグループで唄われています。
-
大津絵踊り
大津絵は、寛永年間1624年頃、宿場町大津より逢坂の関追分辺りで大津絵師により仏画で売られ、その後日本の代表的な民画として継承されています。「藤娘」「鬼の念仏」「鷹匠」などのお面をかぶって踊る「大津絵節」は、江戸時代後期大津の花街から生まれ、全国的に流行しました。
-
大津祭り曳山お囃子
大津祭りは、天孫神社の祭礼として江戸初期に始まり、湖国三大祭の一つです。
大津町衆の心意気と豪華絢爛な13基の曳山が、町中を「コンコンチキチン」と笛、太鼓、鉦でお祭り気分を盛り上げます。 -
カトレア サクソフォン カルテット
滋賀・京都在住の音楽大学出身のメンバーによって結成。クラシックを得意としていますが、ポップスやジャズなどあらゆるジャンルの音楽を演奏し、好評を博しています。関西を中心に、芸術鑑賞教室やコンサートを行うほか、お祭りや地域のイベントなどさまざまな場所で積極的に活動しています。
-
和太鼓
・和太鼓集団・あづち信長出陣太鼓
織田信長の出陣をイメージし、ほら貝を合図に出陣する和太鼓集団。
・水口囃子・八妙会
水口囃子は日本三大お囃子で、コミカルに鉦・笛・太鼓を打ち鳴らす。 -
龍谷大学バトンチア SPIRIS
部員20名で活動する龍谷大学バトンチアSPIRITSは学内行事での演技披露をはじめ、イベント等への出演を行っています。バトントワリングとチアリーディング両方の魅力をお楽しみいただけます。
-
シンガーソングライター yokko
滋賀県甲賀市水口町出身のシンガーソングライター。手話を取り入れた独自のスタイルで、コンサートホールだけでなく、教育現場や福祉施設での講演会など積極的に活動を行っています。